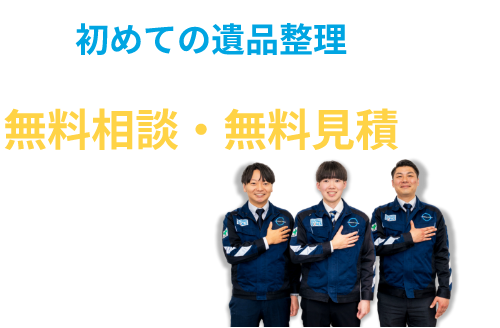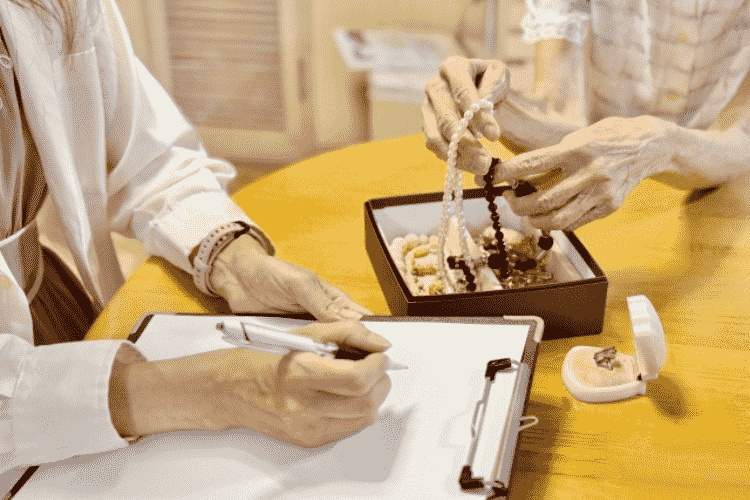賃貸物件に住んでいた親族が亡くなった際に、遺品整理はどう進めるべきか気になる人は多いでしょう。悲しみに暮れる間もなく直面するのが、故人が住んでいた部屋の片付けです。
特に賃貸住宅の場合、家賃の支払いや退去期限が迫ってくるため、迅速な対応が求められます。そのため、持ち家の場合と比べるとスケジュールを念入りに立てたうえで進めなければなりません。
本記事では、賃貸物件における遺品整理の進め方や注意点について、以下の内容を解説します。
- 賃貸物件での遺品整理を進める流れ
- 遺品整理から退去までに発生する費用の内訳
- 遺品整理に取り組むべき人と注意点
遺品整理をスムーズに進めるためにも、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件での遺品整理を進める流れ

賃貸物件の遺品整理は持ち家とは異なり、大家や管理会社との連携が不可欠です。退去期限という時間的な制約があるため、効率的なスケジュール管理が求められます。遺品整理の流れは、以下のとおりです。
- 契約者の死亡を管理会社・大家へ連絡する
- 賃貸契約の名義確認と解約手続きをおこなう
- 遺品整理作業をおこなう
- 退去前に原状回復や清掃をおこなう
- 鍵の返却と最終確認を済ませる
まずは全体の流れを把握し、各段階でやるべきことを明確にしていきましょう。
契約者の死亡を管理会社・大家へ連絡する
契約者が亡くなった事実は、可能な限り早く管理人や大家へ知らせる必要があります。早急に連絡を入れることで、家賃の発生期間や退去日に向けた手続きをスムーズに進められるためです。
連絡の際は、以下の内容を確認しましょう。
- 現在の契約状況
- 解約手続きの流れ
- 退去期限
- 鍵の返却方法
- 立ち会いの有無など
後々の「言った言わない」のトラブルを防ぐために、話し合いで決定した内容は、メールなどの記録に残る形で保存しておくことが大切です。
賃貸契約の名義確認と解約手続きをおこなう
賃貸借契約書を確認し、誰が正式な契約者になっているかを把握しておきましょう。契約者本人が亡くなった場合は、相続人または連帯保証人が中心となって解約手続きを進めることになります。
手続きする際は、死亡の事実が確認できる除籍謄本や医師の診断書、手続きする人の本人確認書類などが必要です。解約日が決定するまでは家賃が発生し続けるため、無駄な出費を抑えるためにも早めの日程調整が重要になります。
遺品整理作業をおこなう
退去予定日までに部屋を明け渡せるよう、計画的に遺品の整理と片付けを進めていきます。効率よく作業するには貴重品や重要書類、思い出の品を最初に見つけ出し、その後に家具や家電の整理に移る手順がおすすめです。
遺品は法的に相続財産となるため、独断での処分はせず、親族と相談しながら進めるようにしましょう。遠方に住んでいて通うのが難しい場合などは、専門の遺品整理業者への依頼を検討するのも有効な手段です。
作業前後の様子を写真に残しておくと、親族間での認識のズレによるトラブルを未然に防げます。
退去前に原状回復や清掃をおこなう
部屋を退去する際は、原則として借りていた側が原状回復にかかる費用を負担します。
原状回復とは、入居時の状態に戻すことを指しますが、経年劣化による部分は考慮する必要はありません。明らかに経年劣化によるものの場合は、そのまま放置しても大丈夫です。
修繕が必要なケースでは費用を負担する基準が異なるため、契約内容の確認は必須です。
孤独死などで体液や強い臭いが染み付いている場合は、通常の清掃では対応できないため、特殊清掃の依頼が必要になります。
鍵の返却と最終確認を済ませる
荷物の搬出と清掃が終わったら、管理会社や大家の立ち会いのもと、室内の状態や破損箇所の最終確認をおこないます。確認の結果、特に問題がないようであれば、預かっていた鍵をすべて返却して引き渡しは完了です。
部屋の状態によっては、後日、敷金で賄えない分の原状回復費用を請求される場合があります。未払いの家賃が残っている場合も併せて請求されるため、支払い方法や期日についてもしっかり確認しておきましょう。
賃貸物件で遺品整理から退去までに発生する費用の内訳

賃貸物件の退去時には、不用品の処分費だけでなく、契約に基づいたさまざまな費用が発生します。退去時に発生する主な費用は、以下のとおりです。
- 不用品処分・遺品整理費用
- クリーニング費用
- 特殊清掃費用
- 原状回復費用
- 損害賠償費用
- 未払い家賃
請求されたとしても冷静に対処できるように、ひとつずつ押さえておきましょう。
不用品処分・遺品整理費用
家具や家電、生活用品などの残置物は、量が多くなるほど処分に手間と費用がかかります。自分たちで処分する場合は自治体のごみ出しルールに従う必要があり、分別や搬出に多大な時間と労力を要します。
遺品整理業者に依頼する場合の費用は、部屋の広さや荷物の量によって変動するのが一般的です。自分たちでできる範囲の整理や処分を事前におこなっておくことで、業者に依頼する際の費用を抑えられます。
クリーニング費用
賃貸物件を退去する際には、次の入居者のために室内全体のハウスクリーニング費用が発生します。具体的な金額は、部屋の間取りや床面積の広さによって設定されているケースがほとんどです。
契約によっては、入居時にクリーニング費用を前払いしている特約が含まれている場合があります。二重払いを防ぐためにも、契約書を見直して費用の支払い条件を確認しておくことをおすすめします。
特殊清掃費用
亡くなってから発見されるまでに時間が経過しているケースでは、特殊清掃が必要になることが多いです。特殊清掃は専用の薬剤や機材を使用するため、一般的な清掃作業と比較して費用が大幅に高額になります。
特殊清掃の費用相場はワンルームで8万円程度、間取りが広いと30万~40万円になることもあります。
汚染状態が深刻な場合は期間を要し、消臭や除菌作業に数日から1週間程度かかることも珍しくありません。作業日数がかかると退去日が遅れて家賃が上乗せされる可能性があるため、早急に手配するようにしてください。
原状回復費用
賃貸借契約の終了時には、借主が部屋を入居時の状態に戻す「原状回復義務」が生じます。ただし、すべての傷や汚れを直すわけではなく、経年劣化や通常使用による損耗は借主が負担する必要はありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、負担区分が判断されます。壁紙の張り替えや床の修繕費などが請求された場合は、経年劣化に該当する部分が含まれていないか確認しておきましょう。
損害賠償費用
故人の死因が自殺などの場合、物件が事故物件として扱われ、次の入居者へ貸し出す際に家賃を下げなければなりません。家賃下落の損害が発生したとして、損害賠償を求められることがあります。
損害賠償額の目安としては、事故発生からおよそ2~3年分の賃料減額分とされています。
請求額に納得できない場合は、詳細な見積書の提示を求めたり、弁護士などの第三者機関へ相談したりしてみてください。一方で、病死や自然死など事件性のない亡くなり方であれば、基本的に損害賠償を請求されることはありません。
損害賠償を請求された場合は、まずは請求対象かどうかの確認から始めましょう。
未払い家賃
故人が亡くなった後も、契約解除の手続きが完了する日までは通常どおり家賃が発生し続けます。加えて、生前に滞納していた未払い家賃がある場合は、滞納分も合算して一括請求されるのが一般的です。
未納分の有無については、退去日の打ち合わせや管理会社への連絡のタイミングで明確にしておくと良いでしょう。解約の手続きを先延ばしにすると、誰も住んでいない部屋に家賃を払い続けることになり、退去費用が高額になります。
賃貸物件の遺品整理に取り組むべき人

遺品整理は誰がおこなうのかで揉めるケースは少なくありません。遺品整理に取りかかる際は、法的な観点や契約上の責任から誰が取り組むべきか判断する必要があります。
主に取り組むことになるのは、以下に該当する人です。
- 相続人
- 連帯保証人
- 大家
それぞれの立場における責任と役割について、見ていきましょう。
相続人
故人の残した物品はすべて相続財産とみなされるため、原則として法定相続人が遺品整理をおこなう立場になります。相続人が複数いる場合はトラブルを未然に防ぐために、形見分けや処分の方法について事前に話し合い、全員の同意を得ておくと良いでしょう。
遠隔地に住んでいるなど自分たちでの作業が困難な場合は、委任状を作成して代理人や業者に依頼するのもひとつの方法です。相続放棄を検討している人が遺品を整理・処分してしまうと、単純承認とみなされるケースがあります。そのため、基本的には手を付けないようにしましょう。
連帯保証人
相続人が不在、あるいは連絡が取れない状況では、連帯保証人が代わりに片付けの対応を求められるケースがあります。しかし、連帯保証人には相続人と違って遺品を引き継ぐ法的権利や義務があるわけではないため、慎重な判断が必要です。
まずは賃貸契約書の内容を確認し、自身の責任範囲がどこまで及ぶのかを把握するところから始めましょう。対応に迷う場合は、自己判断で動かずに弁護士などの専門家に法律相談をして、適切な助言を仰ぐのが賢明です。
大家
相続人や連帯保証人の両者とも連絡がつかない場合、次の入居者を募集するために、大家や管理会社が残置物の撤去をおこなうことになります。相続人と連絡が取れる見込みがあるなら、後日かかった退去費用や損害賠償の請求が可能です。
相続人全員が相続放棄をした場合、法的な請求権はなくなるものの、道義的責任として任意の支払いに応じてもらえるケースも存在します。
賃貸物件で遺品整理を進める際の注意点

賃貸物件での遺品整理には、法律や契約に関わるいくつかの重要な注意点があります。
- 相続放棄をした人が手を付けると相続承認とみなされる可能性がある
- 遺品整理の前に賃貸物件の契約内容を確認しておく
- 特殊清掃が必要な場合は専門業者に依頼する
- 賃貸物件の退去日までに完了させる
知らずに進めると、思わぬトラブルや追加費用の請求につながりかねないため、ひとつずつ押さえておきましょう。
相続放棄をした人が手を付けると相続承認とみなされる可能性がある
相続放棄を決めている人が遺品を安易に処分や売却、あるいは持ち帰ると、法的に「財産を相続する意思がある」とみなされる可能性があります。借金などの理由で相続放棄を検討している場合は、遺品整理に着手する前に家庭裁判所で正式な申述手続きを済ませることが重要です。
放棄手続き後であっても、保存行為としての必要最小限の管理は認められる場合があるものの、線引きは非常に曖昧です。どの範囲までなら手を付けて良いか判断が難しいため、司法書士や弁護士へ相談しておくと良いでしょう。
遺品整理の前に賃貸物件の契約内容を確認しておく
作業を始める前に、退去期限や原状回復の範囲、清掃費用の負担区分などが契約書にどう記載されているかを確認してください。物件によっては、入居時にクリーニング費用を前払い済みの場合があり、退去時に追加の支払いが不要なケースも考えられます。
原状回復の費用負担は物件ごとの特約によって大きく異なるため、管理会社や大家と認識を合わせておくことが大切です。手元に契約書がない場合は、入居時に交付された重要事項説明書の控えを取り寄せて確認しましょう。
特殊清掃が必要な場合は専門業者に依頼する
遺体の発見まで時間が経過していた現場では、強烈な死臭が発生したり汚れが付着していたりしており、市販の洗剤では対応できません。特殊清掃は、感染症予防のための防護服や専用のオゾン脱臭機などを必要とするため、一般の方がおこなうのは困難です。
適切な処置をせずに退去してしまうと、後に高額な原状回復費用や損害賠償を請求されるリスクが高まります。実績のある専門業者に依頼して臭いや汚れを完全に除去すれば、トラブルなく円滑に退去手続きを進められるでしょう。
賃貸物件の退去日までに完了させる
賃貸契約は解約日が到来するまで家賃が発生し続けるため、遺品整理の期間が長引くほど金銭的な負担が増加します。退去日が決まっているのであれば、そこから逆算して不用品の処分や清掃、各種手続きのスケジュールを組む必要があります。
期限を過ぎてしまうと次の入居予定者に迷惑がかかるなど、管理会社との深刻なトラブルに発展しかねません。万が一、期日までに片付けが終わりそうにない場合は気付いた時点ですぐに管理会社へ相談し、指示を仰ぐようにしましょう。
賃貸物件における遺品整理についてまとめ

賃貸物件での遺品整理は、退去期限が設けられていたり退去日までに家賃が発生したりなど、さまざまな制約があります。退去までにかかる費用を最小限に抑えるために、段取りよく進めることが重要です。
契約内容を確認したうえで遺品整理をおこなう人の役割を決め、かかる費用を把握しながら進めましょう。自分たちで対応できない部分は専門家の力を借りることも大切です。
京都市で遺品整理をご検討の際は、山本清掃にお任せください。山本清掃では、遺品の仕分けから不用品の処分、特殊清掃まで、経験豊富なスタッフがお客様の状況に合わせてトータルでサポートいたします。
賃貸物件であってもいち早く退去できるようにスピーディに対応し、あらゆるご要望に応えながら進めさせていただきます。お見積もりは無料ですので、お困りの際はメール、電話、またはLINEからお気軽にお問い合わせください。